内装工事業の今昔


建物の高層化と
建築基準法の改正
日本は以前、ほぼ木造建築の建物が主流でしたが、内装工事業が大きく変わったのは建物が高層化され始めた1980年頃に建築基準法で耐火の構造が根本的に変わったことがきっかけでした。
燃える素材や可燃性の塗料の使用が出来なくなり、木材の仕事が大きく減少しました。


仕事内容の移り変わり
昔は内装仕上げ工事という業種はなく、木工事と塗装業者、左官屋や畳屋、タイル屋で構成されていました。
建物の高層化により、建物を軽量にしなければならない問題、人手の問題、工数の問題と様々な観点から、部屋の間仕切りをモルタルやコンクリートブロックを使わない軽量鉄骨・ボードでの施工に変化しました。
そのため、杉原商店の仕事の範囲が広がったのです。
施工を始めるまでの
杉原商店
杉原商店は、内装仕上げ工事と呼ばれていなかった時代は木工事の造作工事を行っていました。
造作工事とは、主に木を加工して柱や天井、部屋の間仕切りを行う仕事です。
造作大工とも呼ばれ家具屋に流れる場合もありますが、杉原商店は木材繊維吸音材を使った天井の貼り上げ工事を行っていました。


現代まで続く
内装業の基礎が完成
もともと材料販売店を営んでいましたが、施工を始めた頃、アメリカで開発された石膏ボードが日本に入ってきました。
その当時、アメリカの高層建築はすべて現在の石膏ボードが使用されていました。
日本では当初ベニヤ板などが使われていましたが、建築基準法が変わり耐火や耐震の観点から石膏ボードの厚みを出し、その基準に到達したことにより今の「軽量鉄骨で枠組みを作り石膏ボードを貼る」というスタイルが確立されました。
壁・床まで
一連で担う仕事に
その仕上げでビニールクロスが開発され、クロス貼りという仕事が確立されていきます。
この流れから木工事や左官屋、塗装業の仕事は大きく減少し、内装仕上げ工事の仕事が増えていきます。
杉原商店が天井を作り、間仕切りやクロス貼りまで行っていた頃、Pタイルという材料が出たことをきっかけに、床仕上げの仕事も行い始めます。


内装仕上げ工事業の確立
そして時代は高層の建物が多く建設されるようになり、それに比例して専門でない下請け業者が増え始め、問題が増加しましたが、当時の建設省が建築基準法で許可制度を導入したのです。
業種別に分類された中に内装仕上げ工事業ができ、それが我々の業種となったのです。
内装仕上げ工事というのは、コンクリートの建物に電気設備、水道設備、防火スプリンクラーなどの設備機器を取り付けた後に、内装仕上げとして行う工事のことです。
建物の仕上げに携わる喜び
杉原商店は、内装仕上げ工事という名称が生まれる前から様々な建物の内装に携わってきました。
建物の完成までに様々な工事業者が関わりますが、建設の最終段階を担う感動はひとしおです。
また、比較的長く使われる建造物に着手している分だけ、その建物に携われる喜びや誇りもやりがいの一つだと感じます。
少しでも内装仕上げ工事業に興味を持ってもらい、少しでも多くこの仕事を担っていただける方が出てくることを心より願っています。


建物の高層化と
建築基準法の改正
日本は以前、ほぼ木造建築の建物が主流でしたが、内装工事業が大きく変わったのは建物が高層化され始めた1980年頃に建築基準法で耐火の構造が根本的に変わったことがきっかけでした。
燃える素材や可燃性の塗料の使用が出来なくなり、木材の仕事が大きく減少しました。

仕事内容の移り変わり
昔は内装仕上げ工事という業種はなく、木工事と塗装業者、左官屋や畳屋、タイル屋で構成されていました。
建物の高層化により、建物を軽量にしなければならない問題、人手の問題、工数の問題と様々な観点から、部屋の間仕切りをモルタルやコンクリートブロックを使わない軽量鉄骨・ボードでの施工に変化しました。
そのため、杉原商店の仕事の範囲が広がったのです。

施工を始めるまでの
杉原商店
杉原商店は、内装仕上げ工事と呼ばれていなかった時代は木工事の造作工事を行っていました。
造作工事とは、主に木を加工して柱や天井、部屋の間仕切りを行う仕事です。
造作大工とも呼ばれ家具屋に流れる場合もありますが、杉原商店は木材繊維吸音材を使った天井の貼り上げ工事を行っていました。

現代まで続く
内装業の基礎が完成
もともと材料販売店を営んでいましたが、施工を始めた頃、アメリカで開発された石膏ボードが日本に入ってきました。
その当時、アメリカの高層建築はすべて現在の石膏ボードが使用されていました。
日本では当初ベニヤ板などが使われていましたが、建築基準法が変わり耐火や耐震の観点から石膏ボードの厚みを出し、その基準に到達したことにより今の「軽量鉄骨で枠組みを作り石膏ボードを貼る」というスタイルが確立されました。

壁・床まで
一連で担う仕事に
その仕上げでビニールクロスが開発され、クロス貼りという仕事が確立されていきます。
この流れから木工事や左官屋、塗装業の仕事は大きく減少し、内装仕上げ工事の仕事が増えていきます。
杉原商店が天井を作り、間仕切りやクロス貼りまで行っていた頃、Pタイルという材料が出たことをきっかけに、床仕上げの仕事も行い始めます。

内装仕上げ工事業の確立
そして時代は高層の建物が多く建設されるようになり、それに比例して専門でない下請け業者が増え始め、問題が増加しましたが、当時の建設省が建築基準法で許可制度を導入したのです。
業種別に分類された中に内装仕上げ工事業ができ、それが我々の業種となったのです。
内装仕上げ工事というのは、コンクリートの建物に電気設備、水道設備、防火スプリンクラーなどの設備機器を取り付けた後に、内装仕上げとして行う工事のことです。
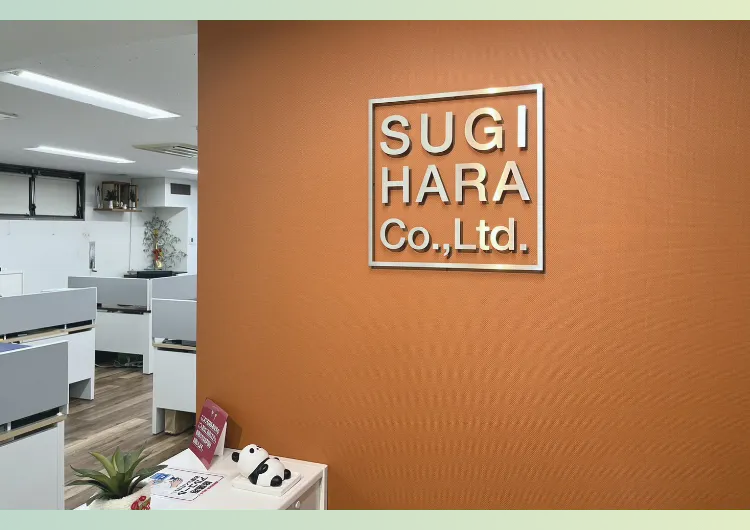
建物の仕上げに携わる喜び
杉原商店は、内装仕上げ工事という名称が生まれる前から様々な建物の内装に携わってきました。
建物の完成までに様々な工事業者が関わりますが、建設の最終段階を担う感動はひとしおです。
また、比較的長く使われる建造物に着手している分だけ、その建物に携われる喜びや誇りもやりがいの一つだと感じます。
少しでも内装仕上げ工事業に興味を持ってもらい、少しでも多くこの仕事を担っていただける方が出てくることを心より願っています。
